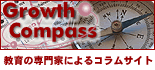たまには子どもと添い寝をしながら、こんなお話を聞かせてあげましょう。 [おもしろ民話集 51]
むかし、とても貧しい村がありました。もとは、ゆたかな村でしたが、何年か前に山が噴火して、作物がとれなくなってしまったのです。
ある秋の日のこと、この村に、お腹をすかせた旅人がへとへとになってたどりつきました。旅人はしばらく何も食べていなかったので、りっぱな庭のある屋敷の戸をたたいて、食べものをわけてもらえないかと頼みました。
ところが、出てきた主人は「だめだね、庄屋のわしだってイモの雑炊しか食えないのだ」「イモのしっぽだけでもいいんです」「人に食わせるものなど何もないよ。それからいっておくが、わしの畑からイモを1本でもぬいてみろ、代官所送りだぞ。近ごろ、村のやつがちょくちょくわしの畑のイモを盗むのじゃ。でもな、だれがやったかすぐにわかる。足あとが火山灰につくからじゃ。作物をだめにした火山灰だが、泥ぼうを捕まえるには、こんな便利なものはない。この貧乏村をあきらめて、山むこうの村へ行くことじゃな」と、旅人を追い返しました。
しょんぼり庄屋の家を出た旅人は、山を越える元気もなく、むだだとわかりながら村の家を一軒ずつたずねてみました。でも、やっぱり食べものをわけてくれる家はありません。やがて日も暮れて、歩きつかれた旅人は、村はずれのあばらやを借りて一晩の宿にしようと、小屋の戸を開けました。すると、一人のおばあさんが出てきました。幸運にも、おばあさんは心のやさしい人でした。雑草の雑炊でしたが、自分の食べる分を、旅人にみんな分けてあげたのです。でも、旅人のお腹はペコペコのままです。おばあさんにすまないと思いましたが、何か他に食べるものがないか頼みました。家には、もう何もありません。おばあさんは、このかわいそうな旅人に、何か食べさせてあげたいと思ったのでしょう。おばあさんは、何か決心したように家を出て行きました。
しばらくしてもどったおばあさんの手には、何本かのイモがありました。おばあさんは、旅人のためにそのイモを煮てあげたのです。旅人はおがむようにして、イモをおいしそうに食べ、何日かぶりに腹がいっぱいになりました。
翌朝、まだ夜もあけないうちのこと。おばあさんは、旅人を起こすと、急いで旅ださせようとしました。旅人は、おばあさんに深くお礼をいいました。ふと、地面に残っている足あとに気がついて、はっとしました。おばあさんの足あとが、あのいじわるな庄屋の畑の方へ続いているのです。
「おばあさん、あのイモは…」「よけいな心配はしなくていいの。早く山を越えて、むこうの村へいきなさい」と、しかりつけるように旅人にいうと、戸をバタンと閉めました。
ちょうどその頃、早起きの庄屋は、いつものように自分の畑のみまわりをしていました。(やや、イモを盗んだやつがいる。どこのどいつだ。うーん、この足あとは村はずれのばあさんのだな。もう、ゆるさない)。たしかに足あとは、おばあさんの小屋のほうへ続いています。
庄屋は、すぐに代官所へ訴え出ようと思いました。でも、その朝はいつになく寒くて、しんしんと冷えこんでいました。(どうせ足あとは消えないから、大丈夫だ)と、家にもどっていっぷくしていました。やがて、日の出の時刻になって、(さて、代官所のお役人さんもやってきたころだろう、そろそろ出かけるとするか)と、戸をあけたところ、いちめんの雪げしきでした。(ややや、足あとが消えてしまっとる。何たることじゃ──)
さあ、だれが雪をふらせたのでしょうか。