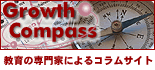たまには子どもと添い寝をしながら、こんなお話を聞かせてあげましょう。 [おもしろ民話集 50]
昔、3人の美しい娘をもった金持ちの男がいました。3人の娘が、それぞれどのくらい自分のことを愛しているか知りたくなりました。そこで、3人の娘たちにきいてみました。1番上の娘は「私の命くらいに」、2番目の娘は「世界をみんなあわせたくらいに」というので、大変満足しました。ところが、3番目の娘は「お肉の料理にそえる塩くらいに」といったのを聞くと、父親はとても怒って「そんな娘はとっとと家を出て行け」と、どなりつけて娘を追いだしたのです。
末娘がしょんぼり歩いていくと、沼のところに出ました。娘はイグサをたくさん摘むと、それで頭からすっぽりかぶる、みのを作りました。こうして、自分のきれいな服を隠して歩いていくと、やがて大きなお屋敷の前にやってきました。そして、自分を召使いにやとってくれないかと頼みました。間に合っているといわれると、「お給金もいらないし、どんな仕事でもします」と、いっしょうけんめい頼みました。それなら雇ってやってもよいといわれ、娘はお屋敷に住みこんで、台所のかたづけなどの仕事をすることになりました。娘は名前を名乗らなかったので、みんなは「あみがさ」と呼びました。
そのころ、近くのお屋敷で舞踏会が開かれることになり、召使いたちも身分の高い人たちが踊るのを見に行ってもよいということで、召使いたちは夜が来るのを楽しみに待ちました。でも [あみがさ] は、疲れているから家で休んでいますといいました。ところが、みんなが出かけてしまうと、娘はあみがさをぬぎ、からだをきれいにして、舞踏会に行きました。すると、舞踏会には娘ほど美しい人はいませんでした。舞踏会には、娘を雇ってくれている主人の息子もきていて、息子は娘を見るなり、すっかり好きになって、娘とばかり踊っていました。でも、 [あみがさ] は、舞踏会が終わらないうちにうまく抜け出して家に帰り、召使いたちがもどってきたときには、あみがさを着て寝ているふりをしました。
朝になると、みんなは [あみがさ] にいいました。「ゆうべ舞踏会に行かないで惜しいことをしたね。あんなきれいな人はいなかったよ。うちの若様ときたら、そのおじょうさんから、一度も目をはなさなかった」「私も見たかったな、そのおじょうさんを」「今夜もまた舞踏会があるから行こうよ、きっとまた来るから」
でも、 [あみがさ] はみんなに、今夜も疲れているから行きませんといい、みんなが出かけてしまうと、娘はあみがさをぬぎ、からだを清めて、また舞踏会へ出かけました。若様は娘がくるのを待ち構えていて、踊るのも娘だけ、いっときも娘から目を離しません。でもその夜も、娘は舞踏会が終わらないうちにうまく抜け出して、家に帰り、召使いたちがもどってきたときには、あみがさを着て寝ているふりをしました。
翌朝になると、みんなはまた [あみがさ] にいいました。「おまえも舞踏会に行っておじょうさんを見ればよかったよ。ゆうべもりっぱな服を着ていて、うちの若様ときたら、一度も目をはなさなかったよ」「私も見たかったな、そのおじょうさんを」「今夜は最後の舞踏会だってよ、いっしょに行こうよ、きっとまた来るから」
でも、夕方になると [あみがさ] は、みんなに疲れているから行きませんといい、みんなが出かけてしまうと、娘はあみがさをぬいで、からだを清めて、また舞踏会へ出かけました。若様は大喜び、踊るのも娘だけで、いっときも娘から目を離しません。ところが娘は、名前を聞かれても答えず、どこに住んでいるかもいわなかったので、若様は指輪を娘にやって、もう一度あえないなら、死んでしまうといいました。それでも娘は、舞踏会が終わらないうちにするりと抜け出して家に帰り、召使いたちがもどってきたときには、あみがさを着て寝ているふりをしました。
翌朝から若様は、娘がどこにいるかを探しまわりました。どこへいっても、誰にたずねても、娘の消息はわかりません。そしてとうとう、若様は娘恋しさに病気になってしまいました。召使いたちは料理番のおばさんに「若様におかゆを作ってあげてよ。あのおじょうさん恋しさに、死にそうになってるんだから」といわれておかゆをこしらえていました。そのとき、 [あみがさ] が入ってきて「私に作らせて」といいました。料理番のおばさんはことわりましたが、何度もせがまれて、やっと承知しました。娘はおかゆを作ると、おばあさんが若様のところへ持っていく前に、あの指輪を中に落としたのです。
若様がおかゆを食べると、底から自分が娘にあげた指輪が出てきました。「このおかゆを作ったのは誰だ!」若様がどなると、「私です」とおばあさんがおそるおそる答えると、「お前じゃない、正直にいわないと許さないぞ」「実は、 [あみがさ] なんです」「すぐに呼んでこい」。
[あみがさ] が若様の前にやってくると、若様は「お前がこのかゆを作ったのか?」「はい」「この指輪はどこで手に入れた?」「ある方からいただいたものです」「お前はいったい誰なんだ?」「それでは、お目にかけましょう」こういって娘があみがさをぬぎすてると、あの美しく着飾ったおじょうさんが立っていました。
こうして若様の病気はたちまち治って、まもなく二人は結婚することになりました。すばらしい婚礼で、近くから遠くからたくさんの人たちが招かれました。その中には [あみがさ] の父親も入っていました。娘は、料理番のおばさんに「お願いだから、肉料理に塩を入れないで」と頼みました。式がめでたく終わって、お客さんはみんなテーブルについて肉料理を食べはじめましたが、まるで味がなくて食べられません。
[あみがさ] の父親は、肉料理に手をつけ、味がないのでほかの皿に手をつけかけた時、急にオイオイ泣き出したのです。驚いた若様が近づき、「どうかしましたか?」「わしは、一人の娘を持っていましたが、ある時その娘に、私をどのくらい愛しているかとたずねたことがありました。するとその子は、[肉料理にそえる塩くらい] といったもので、私は愛のない娘だと思って追いだしてしまったのです。今わかりました。あいつは誰よりも私を愛してくれてたんですな。もう死んでしまったと思うが……」
その時、 [あみがさ] は「お父さん、その子はここにいますよ」と、飛んでいって父親に抱きついたのでした。