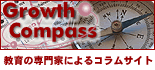私の好きな名画・気になる名画 14

ゴッホやセザンヌと並び、後期印象派の代表的な画家として評価の高いフランスの画家ゴーガンは、はじめは「日曜画家」でした。24、5歳から34、5歳の頃までは、パリで株式の仲買人として働き、おもに休日に好きな絵をかいていたのです。でもその頃から、サロンや印象派の展覧会にも入選し、一部の画家たちから認められてはいました。
そして、1882年35歳の時、突然会社をやめて画家になる決意をします。そのころ、子どもが5人もいたため生活が急に苦しくなりました。ゴーガンが画家になるのを激しく反対したデンマーク人の奥さんは、子どもを連れて故郷に帰ってしまいました。
その後数年間、ゴーガンは北西部のブルターニュでひどい暮らしをしながら黙々と絵を描き、やがてルーアンやポンタベンなどフランス各地を歩いたり、中南米へでかけたり絵の修行をつづけました。一時は印象派的な絵に刺激を受けましたが、これにあきたらず平面的な彩色で装飾的な絵に変わってきました。1888年には、ゴッホの弟テオの援助で、南フランスのアルルでゴッホと共同生活をしましたが、お互いの頑固な性格がわざわいして、わずか2か月で終局をむかえてしまいました。
ゴッホと別れてブルターニュにもどったころから、ゴーガンは都会の文化的な世界や社交をきらい、素朴な未開人の生活にあこがれるようになりました。もともとゴーガンの母方の祖母は南米のペルー人で、ゴーガンも6歳までペルーで心優しい親戚の乳母たちと暮らしていたために、原始的な生活をなつかしむようになっていたのでしょう。1891年、絵の競売で得たわずかのお金をふところに、南太平洋に浮かぶタヒチ島に渡りました。そして、現地に住む人々をモデルに、たくさんの絵を描きました。ここでの生活のありさまは「ノア・ノア」(かぐわしき香り)という本や多くの手紙に残されています。
この「イア・オラナ・マリア」(タヒチ語で「アベ・マリア」の意味)も、タヒチでの暮らしをはじめて数か月後に描いた作品です。さまざまな色彩に満ちあふれた、なんと華やかな絵なのでしょう。ゴーガンは、この絵について、友人にこんな手紙を送っています。「黄色い翼をしたひとりの天使(画面左奥の翼のある人)が、二人のタヒチ人の女に、やはりタヒチ人のマリアとイエスを指し示しているところを描いたものだ。やはり、マリアもイエスもタヒチ人。彼らはみな裸の上にパレオをまとっている。パレオというのは、花もようのついた布のことで、それを腰のところに巻きつける。背景はきわめて暗い山と花咲く木々、濃い紫の道と、前景はエメラルドグリーンで、左手前にバナナがある。私は、この作品を割りと気にいっている」と書いているので、ゴーガンにとっても会心の作品だったのでしょう。
ゴーガンははっきり意識して、タヒチ人のマリアとキリストを描きました。文明に毒されない未開の島の人々をかきこむことにより、残してきた妻子や友人たちの暮らすヨーロッパ世界との別離を意味しているのかもしれません。さらに、マリアとキリストに手を合わせて礼拝している二人の女性は、仏教のお祈りの姿(ジャワ島のボロブドール寺院にある、仏陀にあいさつをする僧の彫刻をモデルにしています)で、「総合主義の美学」といわれるゴーガンの真骨頂を示している絵でもあるようです。
しかし、ゴーガンにとってタヒチでの暮らしは必ずしも快適なものではありませんでした。すでにフランスの植民地として文明化されつつあり、より原始的な生活を求めてもっと奥地の小屋に住んで、原住民と全く同じような暮らしをしながら、土地の風景や人々の絵を描き続けました。そのうちお金がなくなり、伯父の遺産を受け取るために1893年にパリへもどり、タヒチ展を開いたりしましたが、絵はほとんど売れませんでした。失意のうちに2年後、またタヒチに戻って、また原始的な暮らしを続けました。
しかし、タヒチでの生活にもあきたゴーガンは、1901年、さらに未開の離れ小島に移り住みましたが、孤独と生活の苦労と病気に悩みながら、1903年ひとりぽっちで息を引き取りました。
一部の人たちに評価をされてはいたものの、ゴーガンの未開人の姿や生活とともに描かれたたくさんの絵が、洗練された文明人であるパリの多くの人たちを驚かせ、感銘を与えるようになるのは、死後何年もたってからのことでした。