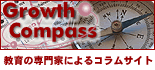「おもしろ古典落語」の85回目は、『もう半分(はんぶん)』という「お笑い」というよりちょっと怖いお話の一席をお楽しみください。
江戸の隅田川の永代橋のたもとに、夫婦二人きりの小さな居酒屋がありました。「こんばんは」「やぁ、おいでなさい八百屋さん。こん夜は、ずいぶんと遅うございますな」「へぇ、ちょっと用足しに手間取りましてな。こちらの前を通ると、もうがまんができなくて入ってきたんですよ。すみませんけど、いつもの通り、半分いただかせてもらいたいんで」「ええ、よろしゅうがす、どうぞ」「へへぇ、ありがとうござい…、うまいですね、こちらのお酒は、うまくって安いときてる。ほんとは飲まないつもりだったんですがね……、へぇ、もう半分」
「えー、お客さんに向かってはなはだ失礼ですがね、うちへも、ずいぶんお客さんがくるけど、半分ずつの人は、あなただけですよ。ちゃんと量りますから、一杯も半分も、おんなじなんですがね」「へへへ、それがね、酒飲みっていうのはいやしいもんで、1杯ずつ3杯飲むより、半分ずつ6杯にすると、なんだか余計に飲める気がしましてねぇ、すみませんが、もう半分」というぐあいで、6杯ばかり飲むと、すっかりいい気持になった白髪まじりの八百屋のじいさんは、礼をいって帰っていきました。
じいさんが帰った後、店の片づけをしていると、なんと、じいさんの座っていたところに、ふろしき包みが置き忘れてあります。よく見ると、小判で五十両という大金が入っています。当時は、十両盗めば首を切られた時代です。「ははぁ、あのじいさん、だれかに金の使いでも頼まれたらしい。気の毒だから」と、追いかけて届けてやろうとすると、奥から女房が顔を出してきました。「ちょっとこっちへおいでよ、おまえさん」「なんだい?」「おまえさんは、人間が正直すぎるよ。わたしはこんな身重で、もういつ産まれるかわからないから、金はいくらでもいるよ。しじゅう貧乏暮らしで、おまえさんだって嫌になったといってるじゃないか。じいさんが取りにきたら、そんなものはなかったと、しらばっくれりゃいいんだよ。あたしにまかせときな」
女房に強くいわれれば、亭主は気がとがめながらも、自分に働きがないだけに文句がいえません。そこへ、真っ青になったじいさんが飛びこんできました。女房が「金の包みなんてそんなものはなかった」といっても、じいさんはあきらめません。「わたしは、いぜん深川で、少しは知られた八百屋でございました。それが、酒が好きなもんで、かせぐそばから飲んじまって、とうとう店を閉じて、天秤棒かつぎの八百屋になってしまいました。この金は、娘が私を楽させるため、身を売って作ってくれたものなんです。あれがなくては娘の手前、生きていられないので、どうか返してください」と泣いて頼んでも、女房は聞く耳を持たず、追い返してしまいました。
亭主はさすがに気になって、とぼとぼ引き返していくじいさんの後を追いましたが、すでに遅く、永代橋からドボーンと、身を投げてしまいました。「しまった、悪いことをした」と思っても、あとの祭り。いやな心持ちで家に帰りました。それから2、3日すると女房が産気づき、産んだ子が男の子。顔を見ると、歯が生えて白髪まじりで「もう半分」のじいさんと、うり二つです。それがギョロっとにらんだものだから、女房は「ギャーッ」と叫んだまま、あの世の人になってしまいました。
泣く泣く葬式を済ませると、赤ん坊は丈夫に育ち、あの五十両を元手に店も新築して、奉公人も置く身分になりました。ところが、こまったことがひとつありました。赤ん坊をまかせておいた乳母が、五日と居つきません。何人目かに、ようやくわけを聞き出すと、赤ん坊が夜な夜な行灯(あんどん)の油をペロリペロリとなめるので「こわくてこんな家にはいられない」といいます。さてはと思ってその真夜中、戸を少しあけて見張っていると、丑三ツの鐘と同時に赤ん坊がヒョイと立ちあがり、行灯から油皿をペロペロとなめるではありませんか。思わず持っていた棒をふりあげ「こんちくしょうめッ」と飛び出すと、赤ん坊がこっちを見て油皿をさしだし……、
「もう半分」
「9月13日にあった主なできごと」
1592年 モンテーニュ死去…世界的な名著 「随想録」の著者として、400年以上たった今も高く評価されているフランスの思想家モンテーニュが亡くなりました。
1733年 杉田玄白誕生…ドイツ人の学者の書いた人体解剖書のオランダ語訳『ターヘル・アナトミア』という医学書を、苦労の末に『解体新書』に著した杉田玄白が生まれました。
1975年 棟方志功死去…仏教を題材に生命力あふれる独自の板画の作風を確立し、いくつもの世界的な賞を受賞した版画家 棟方志功が亡くなりました。