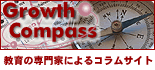今年のフランス・カンヌ映画祭で、グランプリの栄誉に輝いた「殯(もがり)の森」(河瀬直美監督作品)は、次のような物語です。
[奈良県東部の山間地。自然豊かなこの里に、旧家を改装したグループホームがある。ここでは軽度の認知症を患った人たちが、介護スタッフとともに共同生活をしている。その中の一人、しげきは、33年前に妻が亡くなってからずっと、彼女との日々を心の奥にしまいこみ、仕事ひとすじに生きてきた。
そして今、しげきは亡き妻の想い出と共に静かな日々を過ごしていた。誰も立ち入ることの出来ない、しげきと妻だけの世界。そのグループホームへ新しく介護士としてやってきた真千子もまた心を閉ざして生きていた。不慮の事故で子どもを亡くしたことがきっかけとなり夫との別れを余儀なくされたのだ。つらい思いを抱えながらも、真千子は毎日を懸命に生きようとしていた。
ある晩、亡き妻の思い出の詰まったリュックサックを、そうとは知らず何気なく手にとった真千子を、しげきは突き飛ばしてしまう。自信を失う真千子を、主任の和歌子は静かに見守り「こうしゃんなあかんってこと、ないから」とそっと励ます。次第に、真千子は自分の生き方を取り戻し始める。そして毎日の生活の中で、やがて心打ち解けあう、しげきと真千子。
ある日真千子は、しげきと一緒に妻の墓参りに行くことになるが、途中で真千子が運転する車が脱輪してしまう。ここから動かないようにとしげきに念を押して助けを呼びにいった真千子。だが車に戻ると、そこにしげきの姿はなかった。ようやく探し出したしげきは、真千子のことばに耳を傾けようとせず、どんどん森の奥へ奥へと入っていく……](パンフレットおよび公式サイトより)
そして、道に迷った二人を待ち受けていたのは、森の洗礼ともいうべきさまざまな出来事。いつしか真千子の心は、しげきを守り無事にホームにもどらなければという介護者の意識から、しげきの心に寄り添い、しげきの心のままにしてあげようという気持ちに転じていく。しげきのリュックサックから出てきた1973年から2007年までの34冊の冊子。それは、妻が亡くなってからの毎年の日記なのだろう。33年の歳月を記録する冊子を抱きながら、微笑むように妻の眠る森の土に返ろうとするしげきを、真千子は尊い生きかた(死にかた)として見守る……(幕)
カンヌ映画祭で「鳴りやまぬスタンディングオーベーションで迎えられた」のはどんな作品なのだろうという興味もあり、2週間ほど前に、この話題の映画を見にでかけました。しかしながら、老人ホーム、認知症、生と死といった重いテーマを扱った若い女性監督のこの作品に対し、大半の日本人は拒否反応を示したようです。
この評価の大きな差は何なのかを考えてみました。以下、箇条書きしてみます。
(1) 映像が中心でセリフの少ない映画なのに、そのセリフがとても聞きとりにくかったこと。おそらく、カンヌでは、セリフは字幕スーパーで知らせていたのでしょう。日本語の字幕スーパーでセリフを入れたら、同じ土俵で勝負できたにちがいありません。
(2) 日本人には、当然のように思っている自然の美しさ、風の吹き渡る風景・うっそうとした生と死のはざまのような森・陽光に立ち上る草いきれ・茶畑をはじめ緑のすばらしさ。そんな日本美をしっかり記録した映像の確かさは監督の功績といってよいでしょう。
(3) キリスト教的死生観とは異なる、森に同化するというアニミズム的死生観が、欧米人には新鮮に思えたのではないでしょうか。私にはなぜか、例の歌「千の風になって」を絶賛する欧米人とダブッてみえてしかたがありません。
(4) 妻の死後33年間も、妻との生前の楽しい思い出だけを生き甲斐としている主人公への驚き、そして妻と死後も同化したいと願う男にたいする理解と容認をしめす真千子、二人への共感が、テーマを漠然としか捉えられない日本人以上に、欧米人には強烈なインパクトを与えたのではないでしょうか。
私は、3年近く前に、4年半もの闘病後、肺がんでなくなった妻と、生と死と向き合う数年間をすごしてきたこともあり、多少の違和感はありながらも、鑑賞後意識から去ってしまう映画が多い中、時間とともにずしりとした重みを感じさせてくれるこの作品を高く評価したいと思っています。
なお、タイトルの「殯(もがり)」とは、敬う人の死を惜しみ、しのぶ時間や場所を意味する言葉。語源は「喪あがり」喪があける意だそうです。ところが外国向タイトルは、[The Mourning Forest] じつに簡潔というか、単純なタイトルです。