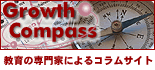10年以上にわたり刊行をし続けた「月刊 日本読書クラブ」の人気コーナー「本を読むことは、なぜ素晴しいのでしょうか」からの採録、第5回目。
☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜★〜☆〜★〜〜〜〜〜〜〜〜☆
● 孤独のさみしさ・いたずらの悔い
すぐれた本にであうと、読後、なぜかぼんやりしてしまうことがあります。それは、きっと、感動に酔っているからです。また、その1冊の本から、ある衝撃を受けたからです。そこで、今回は、本が読者の心をゆさぶることの大きさについて考えてみましょう。
小学校の国語の教科書に収められている読書教材のひとつに、新美南吉の 「ごんぎつね」 があります。人間と動物との心の通いあいをえがいた名作です。
さて、この作品を読んでいくうちに、子どもたちは、いろいろな場面にぶつかり、いろいろなことを考えます。
まず、はじめに、兵十がせっかくとった魚を、キツネのごんがいたずらをして、みんな川へ捨ててしまうところでは、子どもたちはみんな、ごんのいたずらをにくみ、いたずらの悪を考えるでしょう。と同時に一方では、「ごんは、ひとりぼっちだから、きっと、さみしいのだ」 などと、いたずらをするごんの気持ちを、やさしく思いやるでしょう。
つぎに、兵十のおっかあが死んで、兵十は、あの魚を病気のおっかあに食べさせてやりたかったのだ、ということを知ったごんが、「ちょっ、あんないたずらをしなけりゃよかった」 と後悔するところでは、多くの子どもが、自分もいたずらをして後悔したことがあることを思いだしながら、悔いているごんの心に思いを寄せるでしょう。そして、兵十へのつぐないの気持ちで、ごんが、魚やクリやマツタケを、毎日こっそり兵十の家へとどけるところでは、子どもたちはさらに深く、ごんの心を考えるでしょう。また、ごんと兵十の、ひとりぼっちどうしのことをも考えるでしょう。
ところが、兵十が神さまにお礼を言おうとするのを見て、ごんが 「おれが、クリやマツタケを持っていってやるのに、そのおれにはお礼を言わないで神さまにお礼を言うんじゃぁ、おれはひきあわないなあ」 と思うところでは、子どもたちは、せっかくのしんせつに報いを求めるごんに、批判の目を向けるでしょう。
● 善意が通じあわない悲しさ
でも、最後は、兵十に火なわ銃でうたれ、「ごん、おまえだったのか。いつも、クリをくれたのは」 という兵十の声に、ぐったりと目をつぶったままうなずいて死んでいくごんに、すべての子どもがやさしく心をふるわせ、すべての子どもが、この作品の悲しい世界に心からひたります。
以上のようにたどってくると、ひとつの作品が、いかに、いろいろなことを語りかけてくるかがわかります。また、読みすすむ読者の心を、いかにゆすぶるかがわかります。つまりこれが、すぐれた作品を読むことの価値であり、これが読者を酔わせるのです。
ところで、生活のなかの実経験で、心から怒り、心から同情させ、心から悲しませるような事件にめぐりあうことが、どれほどあるでしょうか。たとえば、作品 「ごんぎつね」 が訴える、ひとりぼっちの孤独さや善意が通じない悲しさにしても、これを日常生活のなかで考える機会が、どれほどあるでしょうか。一般的にいって、それは、めったにないことであり、だからこそ、文学作品などを通じて代理経験することの意義の大きさが、指摘されているのです。
世界の思想に多くの影響をあたえたフランスの思想家モンテーニュは、名著 「随想録」のなかで 「私は、本のなかからこそ、多くの人生を学んだ」 という意味のことを言っていますが、これは、ひとりモンテーニュにかぎったことではないでしょう。
読書が考える人間をつくるというのは、まったく真実です。子どもたちに、1冊でも多くのすぐれた本にめぐりあわせて、すこしでも多く、心をゆさぶられる機会をもたせてやりたいものです。「ごんぎつね」 1冊に酔わせただけでも、これほど多くのことを考えさせることができるのですから。