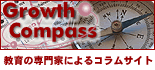10年以上にわたり刊行をし続けた「月刊 日本読書クラブ」の人気コーナー「本を読むことは、なぜ素晴しいのでしょうか」からの採録、第57回目。
☆〜〜〜〜〜〜〜〜★〜☆〜★〜〜〜〜〜〜〜〜☆
● 本と遊ぶ醍醐味を味あわせる
「うちの子は、マンガか、ごくみじかい物語の本しか読まない。なんとか、もっと本を読むようにならないだろうか」 ──小学校中・高学年の子どもを持つ母親から、こんな相談をよく受けます。
ほんとうのところを言えば、やや手おくれです。子どもが、本を読む楽しさを知った少年、少女として成長していくかどうかは、ふつう、3〜5歳の幼児期に決まってしまうからです。
事実、小学校1年生にあがってきた子どもを見ると、このときすでに本を読むことの楽しさ、おもしろさを知っている子どもは、たとえ、マンガを手にしたとしても、童話や物語の本を読むことを捨ててしまうようなことはありません。
ところが、本の楽しさを知らないまま入学してきて、マンガを手にした子どもは、まちがいなくマンガがすべてになり、童話や物語の本には全くといってもよいほど、興味を示さない子どもになってしまいます。
3〜5歳の幼児期に絵本に親しませることは、ほんとうに大切です。「あのころ、絵本の読み聞かせをしてやればよかった」 と、あとで悔いることのないようにしたいものです。
ところで、では小学校中・高学年になってからでは全く手のほどこしようがないかといえば、そうではありません。
どんな子どもも、おもしろいと思う遊びにはとびつきます。したがって、本を読むことも楽しいとわかれば、“本で遊ぶ” ようになってくれます。
本を読もうとしない子どもには 「この本を読んでごらん」 とすすめるよりしかたがありませんが、このとき、読書を教養的にとらえず、“遊び”としてとらえて、本をすすめることです。“本で遊ぶ”“本と遊ぶ” ことから出発させることが大切です。
その一つに動物文学を楽しませるという方法があります。
たとえば、鹿を撃ち殺そうとする猟師と、いのちがけで仲間を守ろうとする鹿との、生きるものどうしの心のふれあいを描いた 「片耳の大鹿」 。戦争の犠牲になって死んでいく犬のたたかいを描いた 「マヤの一生」。子グマのためにいのちがけで滝つぼに飛び込む母グマの愛を描いた 「月の輪グマ」。このほか 「大空に生きる」 「孤島の野犬」 「大造じいさんと雁」 など、動物のたくましく生きる姿と、人間との心のふれあいを描き、まるで推理小説か探偵小説のように読者をひきつける椋鳩十のたくさんの作品。
人間との5年にもわたる戦いの末にとらえられ、人間が与えた食べものには見向きもせず、山の方を見つめたまま静かに死んでいくオオカミを描いた 「オオカミ王ロボ」 などの 「シートン動物記」。
北国にラッコの生活をとらえながら、エスキモーの子どもとラッコとの愛を描いた 「銀色ラッコのなみだ」 などの岡野薫子の作品。
これらは、動物を擬人化した物語とは異なり、さまざまな厳しい条件のなかでたくましく生きる動物たちをそのまま描きながら、そこに人間をからませたものです。したがって、迫力に富んでいます。
椋鳩十の 「マヤの一生」 「孤島の野犬」 を読んでいると、自分がいつのまにか犬になってしまいます。シートンの 「オオカミ王ロボ」 を読んでいると、自分がオオカミになってしまいます。そして、自分でも気づかないうちに、むしろ、動物たちを死へ追いやる人間をにくむようにさえなってきます。
生命あるものの“生きることの尊厳”への感動が、そうさせるのでしょう。
椋鳩十の動物文学は、今、図書館で子どもたち (小学校中・高学年) にもっともよく読まれているものの一つです。
また、「シートン動物記」 は、もっとも長く読みつがれている動物文学です。
「この犬の話はおもしろかった」「このオオカミの話はおもしろかった」と思えば、もうそれで本を読む楽しさ、本と遊ぶ楽しさを知ったのです。