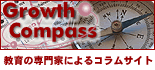10年以上にわたり刊行をし続けた「月刊 日本読書クラブ」の人気コーナー「本を読むことは、なぜ素晴しいのでしょうか」からの採録、第20回目。
☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜★〜☆〜★〜〜〜〜〜〜〜〜☆
● 人間のからだの神秘に目をみはる
お母さん方は、子どもに本を読ませたいと思うとき、まず第一に、童話を中心にした物語の本を考えます。それは、1冊の本から、子どもが、できるだけ大きな感銘を受けることを期待し、その感銘は、文学作品から受けるものが、もっとも大きいと思っているからでしょう。
ところが、じっさいは必ずしもそうではありません。子どもは、伝記や科学物語はもちろんのこと、絵を中心にした図鑑類からも、すばらしい発見の感銘、おどろきの感銘を受けています。
ここに、「ひとのからだ」 「からだのひみつ」 「からだのふしぎ」 などと題した本を読んでの感想文があります。
小学校1〜3年生の子どもたちが書いたものですが、いちように口にしているのは 「こんな本は、はじめてよみました」 「人のからだは、ふしぎでいっぱいですね」 ということです。子どもたちは、赤ちゃんが小さな豆つぶから大きくなること、おへそが、とってもたいせつなものであったこと、のうの王さまがめいれいをくだして手や足がうごくこと、ひふにたまるアカは、ほこりやどろではなく、ひふがしんだものであったこと、かおや手のしわは、としをとって、からだがやせてくるからではなく、ひふの下のあぶらがなくなってできること、小さな舌なのに、あまさや、からさや、にがさや、すっぱさを感じるところは、みんなちがうこと……などに、目を見はっています。そして、人間が生まれてくることの神秘さ、人間のからだのしくみの神秘さに、はじめて心をうたれ、自分で自分のからだを見なおしています。
客観的におどろくだけではありません。たとえば、舌の味を感じる場所のちがいを知った子ども(1年生) は、鏡の前へ行って、本を見ながらじっさいに、さとうやら、しおやらを舌の先にのせたり、奥にのせたり、すを舌のはしのほうにつけてみたりして、自分でたしかめることをくり返しています。
また、骨のことを知った子ども(2年生) は、父や兄といっしょにふろに入ったとき、胸の骨を教えあったり、骨の太さや長さをくらべあったり、関節のしくみを話しあったりして、これも、自分でなっとくすることをくり返しています。
● 文学にはない発見の感銘
このほか、なぜ血は赤いのだろうか、なぜ髪や爪はのびてくるのだろうか、なぜめがねをかけた人と、かけない人がいるのだろうか、なぜ手や足にものがささったら痛いのだろうか、強くぶつけたら、なぜこぶができるのだろうか、悲しいとき、なぜなみだがでるのだろうか、からだにくすぐったいところがあるのは、なぜだろうか……などについて、みんなが考えています。そして、いま読んだ本でわからなければ、ほかの本をもっと読んでみようと言っています。なぜだろう、どうしてだろうという思いが、ひとりひとりの子どもの探求心をよびおこすのです。
これまで、ひとつも気にしていなかったこと、あたりまえだと思っていたこと、ふしぎでもなんでもなかったことを、たった1冊の本にふれたことによって、改めて見なおすようになる。つまり、科学する心を、自分で育てていく。すばらしいのは、からだの本や図鑑を読んで、からだのことについての知識をふやしたことよりも、この科学的に物を見たり考えたりする心を、子どもが、ふくらませてくれることです。このことを、文学作品に要求しても、それを求めることはできず、だから、すべての子どもに、童話などと同じように科学の本を与えることの必要性が説かれているのです。新しいことを知ることの、おどろきとよろこび、これも、すばらしい感銘です。
もしも、子どもがどうしても本好きになってくれないなら、童話などにあわせて、科学の本を与えてみる……子どもが、いくつかのページで発見のよろこびを味わえば、必ず、本の楽しさを知ってくれます。