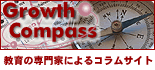大学を卒業してすぐに、私は「社会思想社」という出版社に入社した。「現代教養文庫」という文庫判のシリーズを刊行する出版社で、当時すでに500点近くを出版する中堅クラスの会社だった。今でこそ文庫といえば、百社に近い出版社が手がけているが、当時文庫といえば、岩波書店、新潮社、角川書店の3社が刊行する、古典や定評ある文学作品というイメージが強いものだった。その3社の文庫に続く存在として教養文庫が高く評価されたのは、若者向け人生論から、写真をふんだんに取り入れた旅シリーズ、文学散歩、世界の名画めぐり、科学読み物など、さまざまな分野の書下ろしをメインとするところにあり、高校生や大学生に特に人気があった。仕事は「広告」担当だった。新聞や雑誌に出稿する広告原稿の制作が主だったが、この仕事は出版をトータルで学べるという点で有難い部署だった。編集部ではどんな本を刊行するのか、営業部はどんな売り方をするのか、広告予算はどの程度か、会社の経理面も何となくわかる。ただ、入社後すぐに気づいたのは、出版社というのは、読者とのパイプが皆無に近いということだった。つまり、お客さんは書店に行ってほしい本を買うわけだから、どんな人が購入したのか出版社には具体的な読者がみえない。読者情報を得る唯一の手段は「読者カード」という、本の間に挟み込まれたハガキだけといってもよい。それを頼りに、何人かの人と直接会って話を聞いてみると、教養文庫に、中学生とか高校1、2年生の頃に出会った人ほど、ヘビーユーザーになっている。もっと早い時期、小学生、さらに幼児の時期に出会わすことができたら、もっと大きな効果を生み出すに違いない。私の幼児・児童期の体験から確信に近いものがあった。それから何年か後、編集部に配属されたとき、文庫判の絵本企画を提案した。そして、そんな絵本シリーズで面白さを知った人たちは、必ず現代教養文庫のファンになってくれるはずだと企画会議で力説した。ところが、何度提出しても答えは同じだった。「児童出版社は、老舗の福音館書店、偕成社をはじめたくさんの会社があるけれど、どこもコンパクト判の絵本など出していない。出版しないということは売れないということ。専門の会社がやらないようなことをやるのは無謀」というのがその理由だった。続きは後日(明日を予定)。
児童英語・図書出版社 創業者のこだわりブログ Top > 会社の歴史 > 子ども向け文庫シリーズが作りたい
子ども向け文庫シリーズが作りたい
< 前の記事 「せかい童話図書館」刊行の原点 | トップページ | 次の記事 英国レディバード社との出会い >
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://mt.izumishobo.co.jp/mt-tb.cgi/821
2014年08月
カテゴリー
- おもしろ科学質問箱(36)
- おもしろ言葉のおこり(11)
- おもしろ民話集(108)
- おもしろ落語(141)
- こども科学図書館(11)
- せかい伝記図書館(13)
- みんなのおんがくかい(5)
- セサミえいごワールド(8)
- レディバード図書館(24)
- レディバード特選100点セット(26)
- 偉人の子ども時代(67)
- 会社の歴史(55)
- 業務日誌(47)
- 月刊 日本読書クラブ(64)
- 今週のへぇー !?(38)
- 今日はこんな日(1194)
- 子どもワールド図書館(40)
- 私の好きな名画・気になる名画(27)
- 心の子育て論(130)
- 日常生活(24)
- 日本読書クラブ(13)
更新履歴
月別アーカイブ
Mobile

プロフィール

酒井 義夫(さかい よしお)
| 1942年 | 東京・足立区生まれ |
| 1961年 | 東京都立白鴎高校卒 |
| 1966年 | 上智大学文学部新聞学科卒 |
| 1966年 | 社会思想社入社 |
| 1973年 | 独立、編集プロダクション設立 |
| 1974年 | いずみ書房創業、取締役編集長 |
| 1988年 | いずみ書房代表取締役社長 |
| 2013年 | いずみ書房取締役会長 現在に至る |
昭和41年、大学を卒業してから50年近くの年月が経った。卒業後すぐに 「社会思想社」という出版社へ入り、昭和48年に独立、翌49年に「いずみ書房」を興して40年目に入ったから、出版界に足を踏み入れて早くも半世紀になったことになる。何を好んで、こんなにも長くこの業界にい続けるのかと考えてみると、それだけ出版界が自分にとって魅力のある業界であることと、なにか魔力が出版界に存在するような気がしてならない。
それから、自分でいうのもなんだが、何もないところから独立、スタートして、生き馬の目をぬくといわれるほどの厳しい世界にあって、40年以上も生きつづけることができたこと、ここが一番スゴイことだと思う。
とにかくその30余年間には、山あり谷あり、やめようかと思ったことも2度や3度ではない。なんとかくぐりぬけてきただけでなく、ユニークな出版社群の一角を担っていると自負している。
このあたりのことを、折にふれて書きつづるのも意味のあることかもしれない。ブログというのは、少しずつ、気が向いた時に、好きなだけ書けばいいので、これは自分に合っているかなとも思う。できるかぎり、続けたいと考えている。「継続は力なり」という格言があるが、これはホントだと思う。すこしばかりヘタでも、続けていると注目されることもあるし、その蓄積は迫力さえ生み出す。(2013.8記)