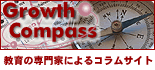今思い起こすと、「レディバードブックス特選100点セット」を刊行した1987年から数年間が、英国レディバード社の最も繁栄していた時期だったように思う。マルコム・ケリー社長のもと、幹部も社員も生き生きと仕事に取り組み、次々と新企画を打ち出していた。1988年の晩秋、私はコンテストで優秀な成績をおさめた当社の営業幹部や営業マン7名を引き連れ、レディバード社を訪れた。私にとって初めての海外旅行でもあったため、特に印象深いものがあった。
レディバード社は、ロンドンの北西約150kmの典型的なイングランド地方の小都市ラフボローにあった。5000坪ほどの敷地に、企画・編集・デザイン部門はもちろん、印刷から製本までもすべて自前で生産する一貫工場を所有していた。出版社というのは、日本でも英国でも、印刷や製本は外注するところがほとんどで、自社工場をもっている会社はきわめて例外的だった。
日本では見たこともないようなB倍判という大きなオフセット印刷機が数台。1枚の用紙から、レディバードブックスが2冊作れるという。驚いたのは、オフセット印刷の刷版が大きな倉庫に保存されていることだった。通常、刷版というのは印刷する都度フィルムからこしらえ、印刷を終えると溶かしてしまうのだが、それを収容するだけの広いスペースがあるのと、ひんぱんに再版されたからなのだろう。
製本工場も目をみはるものがあった。12cm×18cmの上製本に規格化されたレディバードブックスは、完全にオートメーション化されていて、1日10万冊を製造する能力があるという。年間2000万冊以上を世界じゅうに普及させていると聞いていたが、この工場ならと納得できた。
工場見学の終了後、マルコム・ケリー社長はスタッフとともに、われわれをコールズコートという素晴らしいレストランで歓待してくれた。13世紀に建てられたという森の中の風格ある教会の一室、まさにおとぎの国のようなレストランでローストビーフに、高級ワインにと舌鼓をうった。われわれはみな大満足、忘れられない思い出を残してくれた