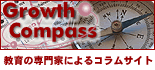「こども科学図書館」の編集にたずさわっていた1977年頃のこと。私の二人の男の子の上が5歳、下が3歳だった。初秋のある日、子どもたちと近所を散歩していると、都会ではめずらしく赤トンボが何十匹となく空を舞っている。子どもたちは、キャッキャといいながら追いかけまわしていたが、そのうち「お父さんつかまえて」というので、悪戦苦闘しながら1匹をつかまえてあげると、もう下の子は大喜び。おっかなびっくり羽根をつかみ、下からながめ、こんどはひっくりかえしながめまわしている。
「こども科学図書館」の編集にたずさわっていた1977年頃のこと。私の二人の男の子の上が5歳、下が3歳だった。初秋のある日、子どもたちと近所を散歩していると、都会ではめずらしく赤トンボが何十匹となく空を舞っている。子どもたちは、キャッキャといいながら追いかけまわしていたが、そのうち「お父さんつかまえて」というので、悪戦苦闘しながら1匹をつかまえてあげると、もう下の子は大喜び。おっかなびっくり羽根をつかみ、下からながめ、こんどはひっくりかえしながめまわしている。
私はさらに、上の子のためにトンボを追いかけ、ようやくつかまえてもどってみると、何と下の子が持っていた赤トンボの羽根がなくなっている。「だめじゃないか。生きものを大事にしなくちゃ」としかりつけたら、「だって羽根をつけてやろうと思ったんだもん!」と、目にいっぱい涙をためてふくれている。私はそれを見てハッとした。
普通、おとながものを考える時は言葉を使う。意識をしていなくても、頭の中であれをこうしてああしてと、さまざまな言葉を思いのまま使って考えをまとめあげる。ところが、幼児はまだ言葉を自由にあやつることができないので、行動が先になりがちなのだ。この時の、子どもの心の動きを想像すると、おそらくこんなことだったはずだ。
赤トンボを手にした時は、(わあ、空をとびまわっていた赤トンボが、いまボクの手の中にいる、うれしいな)と、ながめすがめつしているうちに、「どうして空をとべるんだろう。この羽根があるからだろうか?」と思い、羽根をとったらどうなるかと考える前に、いきなり羽根をとる、という行動をとった。そのうち動かなくなってしまったトンボをみて、いっしょうけんめい羽根をくっつけようとした。
このような日常のちょっとした子どもの行為の中にも、「関心」「疑問」「実験」という、科学の基本的な姿勢があらわれていて興味深い。空を飛んでいる赤トンボに対する「関心」、なぜ空を飛ぶんだろうという「疑問」、羽根をとってみるという「実験」である。ほんらい科学というのは、実験によって法則を知り、法則にしたがって次の考えを展開する過程をたどりながら進歩してきた学問だ。
日常生活の中で、雨や雪、空の色や雲の流れなどの自然現象、動植物に対する興味、自分のからだのはたらきなどについて、驚き、喜び、疑問を感じることは、2歳過ぎころから、ほとんどすべての子どもに見られる。いいかえるなら、すべての子どもが「科学好き」といってよいかもしれない。この「科学への芽ばえ」や子どもの心の動きをしっかり育ててやれるか、反対につみとってしまうかは、紙一重なのだ。
先の赤トンボの例でいうなら、いきなり「生きものを大切にしなくちゃだめじゃないか!」としかりつけてはいけなかった。赤トンボが動かなくなったのを見て、生きものは合体する超合金のおもちゃのように取りはずしのきかないものだと気づき、子ども心にも失敗したと思っていた。だから、しかられたことに対する精一杯の抵抗の涙だったに違いない。