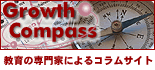今日1月23日は、『叫び』『思春期』『マドンナ』などの作者として、国際的に著名なノルウェーの国民的画家ムンクが、1944年に亡くなった日です。
1863年、ノルウェー南部のローテンに医者の子として生まれたエドバルド・ムンクは、翌年には当時クリスチャニアとよばれていたオスロへ移住して育ちました。しかし、父が神経症だったうえに、幼少のころに母と姉を肺結核で亡くし、自身も虚弱な子どもだったことから、病と死への恐怖がムンクの性格を暗いものにしました。成長するにつれ、北欧の暗く寒い自然や風土、19世紀末の西欧の先行きのみえない世相も影響して頑なに閉じこもりながらも、家事を手伝ってくれた叔母のすすめで、絵を描く楽しさをおぼえるようになっていきました。
1881年、オスロ画学校(のちの王立美術工芸学校)でクローグらに絵画を学びました。「ボヘミアン」という前衛作家・芸術家のグループと交際するようになると、展覧会に出品された『病める少女』(1885〜6年)に代表される「不安」「死」「孤独」を深くみつめ、それを表現する作品を多く描くようになりました。この作品は、罵倒されるほどの批判を受けましたが、クローグら一部の人たちがその才能を評価したことで、パリ留学の奨学金をえて、1885年に数週間、1889年には正式にフランス留学をはたしました。パリでは、レオン・ボンナのアトリエに学びながら、ゴーギャン、ゴッホら後期印象派の画家たちに大きな影響を受けました。
1892年にベルリンに移ると、この地で代表作『叫び』を描きました。「雲が赤く染まった夕暮れ、フィヨルドのほとりを重い気分で歩いているとき、自然を貫く大きな叫びを聞いた。その幻聴をそのまま叫ぶ血の色で描いたのがこの作品」とムンクは語り、大胆な遠近法により、劇的な効果を盛り上げています。ベルリン芸術家協会の展覧会に展示されたこの作品のために、オープンから1週間で保守的な協会側から閉会され、スキャンダルとなりました。ところがこの事件がきっかけとなって、ドイツの詩人、画家、評論家の中に、ムンクを擁護する人たちがあらわれ、以後1908年まで、貧しさと闘いながらも国外での活躍がはじまります。嫉妬・孤独・不安・渇き・憂愁……といったような、非絵画的なテーマをモチーフにした挑発的ともいえる野心作を次々に発表していきました。人間の単なる外面的な美を表現するのでなく、悩み、苦しむ「人間の魂」を描こうとしたのでしょう。ムンクのそんな作風は、現代絵画に大きな影響を与え、いまも高く評価されつづけています。昨年5月には、連作「叫び」の1点が、史上最高値の96億円で落札されたと報道されました。
1908年ころから、創作のために身を削りすぎたことで精神状態が不安定になり、アルコールにおぼれるようになりました。そこで、デンマークの著名な精神科医のもとで療養生活を送り、1909年にはノルウェーにもどって後半生をオスロ郊外で過ごしました。しかし、その後の絵の多くは、「世紀末の不安を描いた画家」のイメージとはかけはなれた、明るい絵でした。没後は遺言により、手元に残していた2万点あまりの全作品をオスロ市に寄贈、「ムンク美術館」に収蔵されています。
なお、オンライン「画像検索」では、ムンクのたくさんの作品他を見ることができます。
「1月23日にあった主なできごと」
1866年 寺田屋騒動…2日前に薩長同盟を締結させた坂本龍馬は、宿泊先の京都・寺田屋で、伏見町奉行所の捕り方に襲撃されました。同宿の養女・お龍は風呂から裸のまま2階へかけ上がり危機を知らせました。龍馬は銃で応戦、左手の親指を負傷しながらも脱出に成功しました。
1869年 薩長土肥藩の版籍奉還…諸大名の封建支配が続いていては、真の国家統一はむずかしいと考えた明治政府の首脳木戸孝允や大久保利通らは、その旧主に版籍(土地と人民)を政府に返還させることにしました。この日、薩長土肥4藩主の連名で、版籍奉還の上表文を提出。これをきっかけに、3月までに諸藩主すべてが奉還を願い出ました。