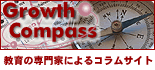今日9月25日は、戦前は「東洋経済新報」のジャーナリストとして、戦後は政治家として独自の業績を残した石橋湛山(いしばし たんざん)が、1884年に生れた日です。
日蓮宗の僧侶の長男として、東京に生れた石橋は、家庭の事情で山梨の田舎に育ち、1902年に上京して早稲田大学哲学科に入学、プラグマティズム哲学者田中王堂に強い影響を受けました。
卒業後は、島村抱月の推薦で「東京毎日新聞」に入社しましたが、同社の内紛にあって1911年に「東洋経済新報」に移ると、まもなくその主幹となって、同社の急進的自由主義の立場を継承しました。国内においては民主的政治体制の樹立をさけび、国外には帝国主義外交を廃止して植民地放棄をさけぶいっぽう、独学でケインズ経済学の理論を学びました。1930年浜口内閣がうちだした金解禁は経済界に大打撃を与えると、経済評論家としての名声を高めました。日本が戦争へと傾斜していった昭和初期にあっては、ひとり敢然と軍部を批判しつづけ、政治・経済・文明はどうあるべきかを主張しつづけ、主幹から同社の専務・社長に就任後、1946年に退くまで35年間、独自の論を展開したのでした。
敗戦後は、経済復興計画を実現しようと、1946年に第1次吉田茂内閣の大蔵大臣となって、ケインズ流の積極財政を展開して、経済再建や生産回復をはかりました。翌年に自由党から衆議院議員に立候補して当選をはたしたところ、戦時中の言論を悪意にとられてGHQから公職追放を命じられました。しかし1951年に解除されると、鳩山一郎内閣の通産大臣を3次にわたってつとめ、1956年12月には自由民主党初の総裁公選で、岸信介をやぶって「石橋内閣」をつくりました。しかし、病に倒れてわずか2か月で退陣。その後は、中国やソ連と友好に力をそそぎ、1973年に亡くなりました。
なお、『昭和史』(戦前編・戦後編 平凡社刊)など昭和史に関する人物論・史論を多く書いている評論家の半藤一利は、『戦う石橋湛山』という著書の中に、石橋が1920年頃の「東洋経済新報」誌上に綴った次の文章を引用し、大正時代末期の先見性ある論調を高く評価しています。
「例えば満州を棄てる、山東を棄てる、その他支那が我が国から受けつつありと考うる一切の圧迫を棄てる、その結果はどうなるか。また例えば朝鮮に、台湾に自由を許す、その結果はどうなるか。英国にせよ、米国にせよ、非常な苦境に陥るであろう。なんとなれば彼らは日本にのみ、かくのごとき自由主義を採られては、世界におけるその道徳的位地を保ちえずに至るからである。その時には、支那を始め、世界の小弱国は一斉に我が国に向かって信頼の頭を下ぐるであろう。インド、エジプト、ペルシャ、ハイチ、その他の列強属領地は、日本が台湾・朝鮮に自由を許したごとく、我にもまた自由を許せと騒ぎ立つだろう。これ実に我が国の位地を九地の底より九天の上に昇せ、英米その他をこの反対の位地に置くものではないか。我が国にして、ひとたびこの覚悟をもって会議に臨まば、思うに英米は、まあ少し待ってくれと、我が国に懇願するであろう。ここにすなわち「身を棄ててこそ」の面白味がある。遅しといえども、今にしてこの覚悟をすれば、我が国は救われる。しかも、これこそがその唯一の道である。しかしながらこの唯一の道は、同時に、我が国際的位地をば、従来の守勢から一転して攻勢に出でしむるの道である。
以上の吾輩の説に対して、あるいは空想呼ばわりをする人があるかも知れぬ。小欲に囚わるることの深き者には、必ずさようの疑念が起こるに相違ない。朝鮮・台湾・満州を棄てる、支那から手を引く、樺太も、シベリアもいらない、そんなことで、どうして日本は生きていけるかと。キリストいわく、「何を食い、何を飲み、何を着んとて思い煩うなかれ。汝らまず神の国とその義とを求めよ、しからばこれらのものは皆、汝らに加えられるべし」 ─と。
「9月25日にあった主なできごと」
1829年 シーボルト国外追放…1年ほど前に、幕府禁制品とされていた日本地図などを国外に持ち出そうとしたこと(シーボルト事件)で、捕えられていたシーボルトが、国外追放・再渡航禁止処分となりました。
1936年 魯迅死去…20世紀初頭の旧中国のありかた・みにくさを鋭く批判した「狂人日記」「阿Q正伝」を著した魯迅が亡くなりました。