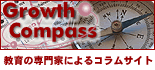今日8月1日は、大正・昭和期に活躍した詩人・小説家の室生犀星(むろう さいせい)が、1889年に生まれた日です。
加賀(石川県)藩の足軽頭だった小畠家の私生児として生まれた犀星(本名・照道)は、犀川のほとりにある真言宗の寺の住職にもらわれ、7歳のとき室生家に養子となりました。「お前はオカンボ(妾の金沢方言)の子だ」とはやされたようで、50歳を過ぎたころに刊行された『犀星発句集』に 「夏の日の匹婦の腹に生まれけり」と詠むほど、犀星はこのハンディを引きずっていたようです。
1902年、13歳のとき金沢市内にある高等小学校を中退、金沢地方裁判所に給仕として就職しました。裁判所の上司の手ほどきで俳句に親しむうち、詩や短歌も手がけるようになりました。18歳で投稿した詩が『新声』という雑誌に掲載されると、8年間勤めた裁判所から福井と金沢の地方新聞社へ転職しましたがあきたらず、1910年21歳のとき、上京しました。
しかし、貧しく、学なく、意地だけが強い犀星に、東京は住みやすいところではありませんでした。北原白秋、山村暮鳥、萩原朔太郎らと親交はもつものの、以後数年の間、東京と金沢の間を転々としながら放浪に近い生活をしたようです。都会の窮乏に耐えられなくなると、実家の寺に舞いもどったのでしょう。
「ふるさとは遠きにありて思ふもの/そして悲しくうたふもの/よしや/うらぶれて異土の乞食(かたい)となるとても/帰るところにあるまじや/ひとり都のゆふぐれに/ふるさとおもひ涙ぐむ/そのこころもて/遠きみやこにかへらばや/遠きみやこにかへらばや」
これは『抒情小曲集』にある『小景異情』という6編からなる連作詩の1編で、最後に実家へもどったとき、自分の居場所は都会にあるべきだと知り、もう故郷には帰らないという決意を詩にしたものでした。
こうして東京にもどった犀星は、1915年『卓上噴水』を萩原朔太郎、山村暮鳥と創刊、翌年には朔太郎と同人誌『感情』を発行してたくさんの詩を発表。1918年には『愛の詩集』『抒情小曲集』、翌年『第二愛の詩集』を出版すると、そのわかりやすい表現と、あふれる抒情は人気を呼び、たくさんの人々に愛唱されるようになりました。
さらに1919年、中央公論に自伝小説『幼年時代』『性に目覚める頃』等を投稿し、注文の入る作家になっていきました。1929年には、初の句集『魚眠洞発句集』を刊行。1930年代から小説の多作期に入り、1935年『あにいもうと』で文芸懇話会賞を受賞。戦後は作家としての地位を確立し、1958年に長編『杏っ子』が読売文学賞、評論『わが愛する詩人の伝記』は毎日出版文化賞を受賞。『かげろふの日記遺文』は野間文芸賞を受賞しています。
さきに掲げた有名な詩「ふるさとは遠きにありて思ふもの〜」の通り、文壇に名をとどろかすようになった後も、1962年に亡くなるまで、犀星は金沢にはほとんど帰ることがありませんでした。
「8月1日にあった主なできごと」
1590年 家康江戸城へ…豊臣秀吉から関東四国をもらった 徳川家康 が、太田道灌の建てた江戸城へ入城。粗末だった城を、じょじょに様式のある城に整えていきました。
1931年 初のトーキー映画…これまでの日本映画はサイレント映画で、スクリーンの横に弁士がついて、ストーリーを語るものでしたが、初のトーキー映画『マダムと女房』が封切られました。