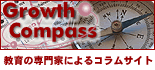今日2月3日は、ドイツの金属加工職人で、活版印刷技術を実用化し、初めて聖書を印刷したことで知られるグーテンブルクが、1468年に亡くなった日です。
紙、活字、印刷機械などが発明されていなかった時代の人びとは、羊や子牛の皮を紙のようにしたものや、パピルスという植物から作った紙に似たものに、手で文字を1字1字書きうつして、本を作っていました。だから、たった1冊の本を作るのも、たいへんなことでした。
やがて、いま使われているような紙が作られるようになってからは、板に文字や絵を彫り、それにインクをつけて紙をのせ、上からおさえつけて印刷するという方法が考えだされました。しかし、新しい本を作るたびに、何十枚、何百枚の板に字を彫るのは、やはり、たいへんな仕事でした。
この印刷の方法に大きな発明を加えて、人類の文化の発展に輝かしい足あとを残したのが、ヨハネス・グーテンベルクです。
グーテンベルクは、1399年ころ、ドイツのマインツ市で生まれました。父は貴族でした。
「同じ字をくり返し彫るのはむだだ。1字1字の活字を作り、それを自由に並べて、何どでも使えるようにしたらどうだろう」
30歳をすぎたころから、印刷の研究をしていたグーテンベルクを発明にみちびいたのは、こんな思いつきからでした。
グーテンベルクは、むちゅうになって、木で活字を作りました。でも、木の活字は、すぐに、すりへってだめになってしまいます。そこで、つぎには、まず活字の鋳型を作り、その鋳型にとかした金属を流しこんで、金属の活字をなん本でも作りだすことを発明しました。さらに、ブドウの実をしぼる圧さく機から思いついて、活字にのせた紙を、手のかわりに機械の力でおしつける印刷機も完成しました。
「これで、たくさんの本が作れる。まず、みんながいちばんほしがっている聖書を印刷しよう」
グーテンベルクは、フストという商人からお金を借りて工場を建て『42行聖書』の印刷にとりかかりました。
ところが、聖書ができあがらないうちに、グーテンベルクは工場を追いだされてしまいました。借りたお金のかわりに、活字も印刷機も工場も、フストに取られてしまったのです。
グーテンベルクは、そののち、こんどは自分の力でもういちど印刷所を建てて『36行聖書』や『カトリコン』という辞書などを作りました。これにより、貴族や金持ちしか買えなかった本が、一般の人でも持てるようになり、学問や文化の普及にたいへん役だったのはいうまでもありません。なお、グーテンベルクの印刷技術は、羅針盤、火薬とともに「ルネサンス3大発明」の一つにあげられています。
以上は、いずみ書房「せかい伝記図書館」(オンラインブックで「伝記」を公開中)4巻「ジャンヌダルク・コロンブス・マゼラン」の後半に収録されている7名の「小伝」をもとにつづりました。近日中に、300余名の「小伝」を公開する予定です。
なお、2月3日の今日は「節分」です。日本中の家庭では夕方から夜にかけて、「福は内、鬼は外」と豆まきの声があちこちで聞えることでしょう。
節分というのは、文字通り、季節の分かれ目を意味する言葉です。立春、立夏、立秋、立冬と、四季ある1年には4回の節分がありますが、立春の前日だけが、節分として残されました。昔の暦では、立春がお正月、節分は大晦日にあたります。節分の鬼を払う悪霊ばらい行事は、平安時代頃から行われている「ついな」から生まれたようですが、やがて、ヒイラギの枝にイワシの頭を刺したものを家の門口に立てておいたり、家族のだれかが年男となって、豆まきをするようになりました。それは、次のような理由からです。
● ヒイラギとイワシの風習
昔、「かぐはな」という悪い鬼がいて、年越しの夜になると、女や子どもを襲って食ってしまうという言い伝えがありました。ところがこの鬼は、イワシの匂いが大嫌いなので、この鬼を防ぐために、雪にも負けない強い木であるヒイラギの葉のついた枝とイワシの頭を戸口にさしました。
● 豆まきの風習
平安時代、京の都の近くの鞍馬山に悪い鬼がたくさん住んでいて、この鬼たちが都に攻めよせてきました。その時、たくさんの豆をまいて鬼の目をつぶし、おいはらったことから、豆まきがはじまったそうです。煎った豆をまいたあと、自分の年齢の数だけ豆を食べると病気をしないともいわれています。