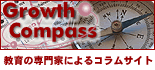今日3月4日は、大正時代の白樺派作家の中では、唯ひとり社会性の高い作品を数多く残した有島武郎(ありしま たけお) が、1878年に生まれた日です。
絵のぐをぬすんだ生徒と、その生徒をやさしくいましめる先生との、あたたかい心のふれあいをえがいた『一房の葡萄』。この物語の作者、有島武郎は、大蔵省につとめる身分の高い役人の長男として、東京で生まれました。
少年時代の武郎は、若いときは薩摩藩(鹿児島)の武士だった父から、きびしく育てられました。しかし、いっぽうでは、早くから外国人の家へ英語を習いに行かされ、また、小学4年生からは学習院へかよわされて、まるで王子のように、たいせつにされました。性格のおとなしい武郎は、父にはぜったいに、さからわなかったということです。
学習院中等科を終えた武郎は、おくれている日本の農業の発展に力をつくすことを考えて、札幌農学校(いまの北海道大学)へ進みました。そして、キリスト教の自由な教育を受けるうちに、自分もキリスト教を信仰するようになりました。武郎が、人間の心のなかの神と悪魔について深く考えるようになったのは、このころからです。
農学校を卒業すると、1年ほど軍隊へ入ったのちにアメリカへ渡って歴史や経済を学び、おおくの外国文学にもふれて3年ごに帰国したときは、キリスト教への信仰を失い、人間の平等な幸福を求める社会主義に心をよせるようになっていました。キリスト教を信仰するアメリカ人が、じっさいの生活では、不平等な資本主義のなかで生きているのを見ているうちに、考えがかわってしまったのです。
武郎は、29歳で東北帝国大学(いまの東北大学)の英語教師になり、3年ごに文芸雑誌『白樺』が創刊されると同人にくわわって小説を書き始めました。そして、37歳で大学をしりぞいたつぎの年に、父と、7年まえに結婚していた愛する妻を亡くしてからは、自分の心と闘うようにして、文学ひとすじにうちこむようになりました。
きびしい自然、つめたい社会、苦しい生活に立ちむかう人間をえがいた『カインの末裔』『生まれ出づる悩み』。新しい自由社会に生きようとする女の業を見つめた『或る女』。愛を求める人間の本能について考えた『惜しみなく愛は奪う』。
武郎は、自己を完成させるために芸術に生き、自分の悩みを、小説、評論、童話に問いかけていきました。しかし、やがて45歳の武郎にまっていたものは、婦人記者を道づれにした自殺でした。芸術家としての自分の力の限界を知り、心の悪魔に負けて、死をえらんだのです。やさしく、はげしい生涯でした。
この文は、いずみ書房「せかい伝記図書館」(オンラインブックで「伝記」を公開中)34巻「夏目漱石・野口英世」の後半に収録されている14名の「小伝」から引用しました。近日中に、300余名の「小伝」を公開する予定です。ご期待ください。
なお、、「青空文庫」には、有島武郎の作品が33点掲載されています。「一房の葡萄(ぶどう)」だけは、この機会にぜひ読むことをおすすめします。