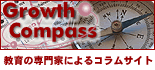今日1月18日は、明治・大正・昭和の3代にわたり、植物採集や植物分類などの研究に打ちこんだ牧野富太郎が、50万点にものぼる押し花や押し草などの標本と20数巻の書物を残し、1957年に94歳で亡くなった日です。
日本の山や野原にはどんな草や花があるのか、80年以上ものあいだ、それを集めたり、絵にかいたり、調べたりしたのが牧野富太郎という人です。このような研究をする人は、たいてい大学を出た学者なのに、富太郎は、小学校にしか行っていません。それも、わずか2年間だけです。あとは自分ひとりで本を読んだり、人にたずねたりしながら勉強を続けました。そして、「日本植物志図篇」全11集、「大日本植物志」「日本植物図鑑」などを次々に著わして、世界中に知れわたるほど有名になりました。
ところが、学歴がないために、31歳で大学の助手にむかえられて、51歳になってようやく講師となり、55歳の時には博士号まで贈られたにもかかわらず、78歳でやめるまで助教授にもなれずに講師のままでした。そのため、月給は安い上に研究費も少なく、いつも借金に苦しんでいました。富太郎は、この大学の閉鎖性にはいきどおりをおぼえましたが、しんぼう強く、自分の意志だけを大切に研究を続けたのです。
この「牧野富太郎」に関する伝記は、いずみ書房のオンラインブックで公開していますので、ぜひのぞいてみてください。
なお、牧野富太郎の記述した文の一部を、「青空文庫」で読むことができます。それぞれの植物に対する細かな観察はむろんのこと、名称のいわれ、和歌、俳句、連歌などにどのように歌われてきたかなど、さまざまな視点でつづられる味わい深い博識に満ちた内容は、魅力的です。青空文庫には9点紹介されていますが、参考として、そのうちの1点「植物知識」に出てくる「ヒガンバナ」の項を、少々長文ですが、以下に掲げてみましょう。
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
秋の彼岸ごろに花咲くゆえヒガンバナと呼ばれるが、一般的にはマンジュシャゲの名で通っている。そしてこの名は梵語(ぼんご)の曼珠沙(まんじゅしゃ)から来たものだといわれる。その訳は、曼珠沙(まんじゅしゃ)は朱華(しゅか)の意だとのことである。しかしインドにはこの草は生じていないから、これはその花が赤いから日本の人がこの曼珠沙をこの草の名にしたもので、これに華を加えれば曼珠沙華すなわちマンジュシャゲとなる。そして中国名は石蒜(せきさん)であって、その葉がニンニクの葉のようであり、同国では石地(せきち)に生じているので、それで石蒜といわれている。
本種はわが邦いたるところに群生していて、真赤な花がたくさんに咲くのでことのほか著しく、だれでもよく知っている。毒草であるからだれもこれを愛植している人はなく、いつまでも野の草であるばかりでなく、あのような美花を開くにもかかわらず、いつも人に忌み嫌われる傾向を持っている。
とにかく、眼につく草であるゆえに、諸国で何十もの方言がある。その中にはシビトバナ、ジゴクバナ、キツネバナ、キツネノタイマツ、キツネノシリヌグイ、ステゴグサ、シタマガリ、シタコジケ、テクサリバナ、ユウレイバナ、ハヌケグサ、ヤクビョウバナなどのいやな名もあるが、またハミズハナミズ、ノダイマツ、カエンソウなどの雅びな名もある。そしてその学名を Lycoris radiata Herb. といい、ヒガンバナ科に属する。右種名の radiata は放射状の意で、それはその花が花茎の頂に放射状、すなわち車輪状をなして咲いているからである。
野外で、また山面で、また墓場で、また土堤などで、花が一時に咲き揃い、たくさんに群集して咲いている場合はまるで火事場のようである。そしてその咲く時は葉がなく、ただ花茎が高く直立していて、その末端に四、五花が車座のようになって咲き、反巻せる花蓋片(かがいへん)は六数、雄蕊(ゆうずい)も六数、雌蕊(しずい)の花柱が一本、花下(かか)にある。下位子房(かいしぼう)は緑色で各小梗(しょうこう)を具えている。
ここに不思議なことには、かくも盛んに花が咲き誇るにかかわらず、いっこうに実を結ばないことである。何百何千の花の中には、たまに一つくらい結実してもよさそうなものだが、それが絶対にできなく、その花はただ無駄に咲いているにすぎない。しかし実ができなくても、その繁殖にはあえて差しつかえがないのは、しあわせな草である。それは地中にある球根(学術上では鱗茎と呼ばれる)が、漸々に分裂して多くの仔苗を作るからである。ゆえに、この草はいつも群集して生えている。それはもと一球根から二球根、三球根、しだいに多球根と分かれゆきて集っている結果である。
花が済むとまもなく数条の長い緑葉が出で、それが冬を越し翌年の三月ごろに枯死する。そしてその秋、また地中の鱗茎から花茎が出て花が咲き、毎年毎年これを繰り返している。かく花の時は葉がなく、葉の時は花がないので、それでハミズハナミズ(葉見ず花見ず)の名がある。鱗茎は球形で黒皮これを包み、中は白色で層々と相重なっている。そしてこの層をなしている部分は、実に葉のもとが鞘を作っていて、その部には澱粉を貯え自体の養分となしていること、ちょうど水仙の球根、ラッキョウの球根などと同様である。そしてそこは広い筒をなして、たがいに重なっているのである。
近来は澱粉製造の会社が設立せられ、この球根を集め砕きそれを製しているが、白色無毒な良好澱粉が製出せられ、食用に供せられる。元来、この球根にはリコリンという毒分を含んでいるが、しかしその球根を搗き砕き、水に晒して毒分を流し去れば、食用にすることができるから、この方面からいえば、有用植物の一に数うることができるわけだ。
この草の生の花茎を口で噛んでみると、実にいやな味のするもので、ただちにそれが毒草であることが知れる。女の子供などは往々その茎を交互に短く折り、皮で連なったまま珠数のようになし、もてあそんでいることがある。
『万葉集』にイチシという植物がある。私はこれをマンジュシャゲだと確信しているが、これは今までだれも説破したことのない私の新説である。そしてその歌というのは、
路の辺の壱師(いちし)の花の灼然(いちしろ)く、人皆知りぬ我が恋妻を
である。右の歌の灼然(いちしろ)の語は、このマンジュシャゲの燃ゆるがごとき赤い花に対し、実によい形容である。しかしこのイチシという方言は、今日あえて見つからぬところから推してみると、これはほんの狭い一地方に行われた名で、今ははやく廃れたものであろう。
このマンジュシャゲ、すなわちヒガンバナ、すなわち石蒜(せきさん)は日本と中国との原産で、その他の国にはない。外国人はたいへんに球根植物を好くので、ずっと以前にこのマンジュシャゲの球根が、多数に海外へ輸出せられたことがあった。