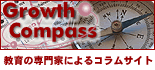今日9月19日は、俳誌「ホトトギス」や歌誌「アララギ」を創刊し、写生の重要性を説いた俳人・歌人・随筆家の正岡子規が、1902年に亡くなった日です。
柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺
柿を食べていると、法隆寺の鐘がゴォーンと鳴ったという、それだけの句です。しかし、静かでもの悲しい秋のようすが、五・七・五の17文字で、みごとに、とらえられています。
この俳句をよんだ正岡子規は,1867年、四国の松山に生まれ、5歳のときに父を失ってからは、母と祖父に育てられました。とくに祖父には、6歳のころから漢学(中国から伝わってきた学問)を教わり、10歳をすぎた子規は、早くも、漢字ばかりの詩をつくって、人をおどろかせるほどになっていました。
12歳で中学へ進んでからも、自分たちの回覧雑誌に、さかんに漢詩を発表しました。ところが、まもなく、政治家をこころざすようになりました。板垣退助らがとなえていた、民主政治を求める自由民権運動に、若い心をもやしたのです。
16歳で中学を退学して東京へでた子規は、つぎの年から大学予備門(のちの第一高等学校)に学び、23歳の年に東京帝国大学(東京大学)へ進みました。政治家への夢をすてて、俳人への道を歩み始めたのは、この青春時代です。のちの文豪夏目漱石と交わり、随筆を書き、和歌や俳諧を学ぶうちに、なかまたちと俳句をつくりあって楽しむようになりました。でも、この青春時代に、すでに、結核でたくさんの血をはいています。
子規は、25歳で大学をしりぞき、日本新聞社へ入って俳諧の話を連載しながら、俳句革新運動を始めました。芭蕉や蕪村の句をのぞけば質が低かった江戸時代までの俳句を、もっと、文学の香りの高いものにしなければいけないと考えたからです。子規のこの熱意は大きな反きょうをよびおこし、古い俳句にしがみついていたおおくの俳人たちの目を、さまさせました。
1895年の3月、子規は、まえの年から始まっていた日清戦争の従軍記者として、大陸へわたりました。しかし、5月、帰りの船の上で血をはいてたおれ、そのごは、脊椎カリエスの身を病床に横たえるようになってしまいました。
俳人子規の花が、さらに大きく開いたのは、これからです。自分の死が近いことを知った子規は、新聞に『歌よみに与ふる書』を連載して、こんどは短歌革新を説き、さらに、自分のけいけんをそのままうつす写生文を書いて文章革新もとなえ、いっぽうでは、新しい自分の句をたくさん生みだしていきました。
痰一斗糸瓜(へちま)の水も間に合はず
これが、病床で『墨汁一滴』『病牀六尺』などの随筆を書き残して、35歳の生涯を終えた、俳人子規の最後の句でした。
なお、正岡子規の作品は、「青空文庫」で、「歌よみに与ふる書」「墨汁一滴」など26点を読むことができます。
この文は、いずみ書房「せかい伝記図書館」(オンラインブックで「伝記」を公開中)34巻「夏目漱石・野口英世」の後半に収録されている14名の「小伝」から引用しました。近日中に、300余名の「小伝」を公開する予定です。ご期待ください。